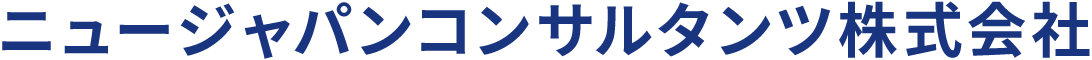10月23日(木)・24日(金)の2日間にわたり、社員28名が参加して視察研修を行いました。

▲熊野本宮大社、鳥居前で記念撮影
当社では、社員の見識や技術力の向上、ならびに部門間のコミュニケーション促進を目的として、年に1〜2回、視察研修を実施しています。業務の枠を超えた学びと交流の場として、毎回テーマを設けて研修を企画していますが、今回の研修テーマは「道」としました。
紀伊・伊勢地方の歴史ある道を訪れ、「道」が果たしてきた役割や意味を考えます。
(1日目)
初日は和歌山駅から大型バスに乗車し、高野山をめざします。
「高野山(金剛峯寺:こんごうぶじ)」は、今から約1200年前の平安時代初期に弘法大師・空海によって開かれた、真言宗の聖地として広く知られています。
また、高野山と高野山へ至る「高野参詣道(こうやさんけいどう)」は、ユネスコ世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部として登録されています。
バスを降り、現地の案内の方とともに、空海が今なお瞑想を続けていると伝えられる「奥之院」へ向かいます。

▲参道の敷石は全国各地の路面電車の軌道で使われていた石だということです。
「奥之院」へ続く参道には、皇室を始め、織田信長や豊臣秀吉、徳川家康をはじめとする名だたる戦国武将や一般の人々、現代の企業など、約20万基とも言われる供養塔が並んでいます。
供養塔の多くは「五輪塔(ごりんとう)」と呼ばれるもので、その形は仏教における宇宙の五大要素「地・水・火・風・空」を表しているそうです。

▲案内の方より様々な供養塔(五輪塔)について説明を受けます。
数百年経った杉林の間から漏れるあたたかい木漏れ日を受けながら、供養塔が並ぶ小道を奥へ進みます。
参道が途切れ、「御廟橋(ごびょうばし)」の奥に「奥之院」が現れます。
この「御廟橋」を渡ることで、俗世から聖域へと足を踏み入れることになるそうです。

▲「御廟橋」から先は、写真撮影・飲食・着帽・大声での会話は禁止されています。一礼をして渡ります。
御廟では、毎日2回(朝6時・昼10時半)、空海に食事を届ける儀式が行われています。
空海が今も生きているという信仰に基づく、世界でも類を見ない継続的な供養の儀式で、食事は精進料理のほかパスタやコーヒーなども供されているそうです。この儀式が実に1200年も続いていることに驚かされます。
奥之院「燈籠堂(とうろうどう)」を抜け、空海が今も瞑想を続けているとされる「御廟」前をとおり、「地下法場(ちかほうじょう)」へ降ります。「身代わり大師像」が両側に並ぶ通路を抜けると、ほどなく御廟の真下、空海に最も近い場所まで行くことができます。
御廟下の石室で座した空海と向き合う形で静かに手を合わせます。厳かな空気に触れたような感覚に包まれます。
その後、「地下法場」から地上へと上がり、「奥之院」をあとにします。

▲「奥之院」からの帰り、豊臣秀吉などが祀られた豊臣家の供養塔を遠くに見ます。(写真奥の小高い場所に立つ五輪塔など)
昼食後、高野山から熊野三山を構成する「熊野本宮大社(くまのほんぐうたいしゃ)」へと向かいます。
熊野三山は「熊野本宮大社」・「熊野速玉大社(くまのはやたまたいしゃ)」・「熊野那智大社(くまのなちたいしゃ)」の総称で、神仏習合(しんぶつしゅうごう)の聖地として知られています。
三社はそれぞれ異なる神を祀りながらも「熊野三所権現」として信仰され、阿弥陀如来・薬師如来・千手観音と結びつけられてきました。
古来より「熊野古道」を通り浄土信仰の巡礼地として栄え、世界遺産の構成施設としても登録されています。

▲移動の途中で立ち寄った「牛馬王子(ぎゅうばおうじ)社」近くの休憩所から熊野古道を望みます。
山間の道を左右に揺られながら熊野本宮大社に到着。
熊野本宮大社は、全国に約3,000社ほどある熊野神社の総本宮で主祭神は家都美御子大神(けつみみこのおおかみ)で、3本の足を持つ「八咫烏(やたがらす)」が神の使いとされ、崇められています。
八咫烏は「導き」、「勝利」、「正しき道」の象徴として日本サッカー協会のエンブレムとして採用されていることでも有名です。

▲拝殿まで158段の階段を登ります。

▲拝殿でお参りをします。社殿はかつて500mほど離れた熊野川の中洲「大斎原(おおゆのはら)」に建っていましたが、明治22年の大洪水で流失し、残った社殿のみが現在の地に移築されたそうです。

▲黒い「八咫烏(やたがらす)ポスト」、実際に手紙を出すことができます。手紙には特別なスタンプが押されるそうです。
「八咫烏ポスト」はご神木である「多羅葉(たらよう)の木」の前にあります。多羅葉の木は、葉の裏に爪などで文字を書いていたことが葉書の語源となり「葉書の木」「手紙の木」とも呼ばれているそうです。
参拝後、旧社殿が建っていた「大斎原(おおゆのはら)」へと向かいます。
旧社殿の跡地は、かつて熊野川・音無川・岩田川の合流点にある中洲で、熊野本宮大社の社殿が壮麗に建ち並んでいた聖地でした。明治22年(1889年)の大水害以前は、約1万1千坪の境内に五棟十二社の社殿、楼門、神楽殿、能舞台などがあり、現在の本宮大社の数倍の規模だったそうです。

▲今から25年前の平成12年(2000年)に高さ約34m、幅約42mの日本一の大鳥居が建てられ、旧社地の目印となっています。

▲現在は中四社・下四社を祀る石祠が2基、建てられています。
大斎原(おおゆのはら)をあとに、本日の宿泊地である新宮市へ向かい、初日の研修を終了しました。
(2日目)
ここから、個人的な話になりますが、
朝、宿泊先から15分ほどのところにある熊野三山の一つである「熊野速玉大社(くまのはやたまたいしゃ)」に出掛けてきました。「熊野速玉大社」の主祭神は速玉大神(はやたまのおおかみ)と事解男大神(ことさかのおのおおかみ)で、再生や浄化の神として信仰されています。熊野川の河口近くに位置し、古来より熊野詣の玄関口として栄えてきたそうです。

▲鳥居の前に来ました。朝、早いためか、境内は人も少ないようです。

▲朱色の美しい拝殿を見ることが出来ます。

▲ここでも「八咫烏」に会う事が出来ました。

▲ご神木の「梛(なぎ)の木」 夫婦円満・縁結びの象徴とされています。お参りは必須です。
「熊野速玉大社」からホテルに戻り、2日目の研修がスタートします。
2日目は趣向を変えてJR特急「南紀」に乗って新宮駅から尾鷲駅まで電車で移動します。発電用ディーゼルエンジンを搭載したハイブリット方式の新型車両の乗り心地は快適で、車窓から見える海沿いの景色を楽しむことができます。
尾鷲駅で再びバスに乗り換え、紀勢自動車道・伊勢自動車道を経由して三重県の賢島へ向かいます。
賢島では2016年5月に開催された「G7伊勢志摩サミット」の記憶を後世に伝えるために設立された「伊勢志摩サミット記念館 サミエール」を訪れます。

▲今では懐かしいG7の首脳たちが写った等身大パネル(撮影は伊勢神宮で行われたそうです。)
館内では係の方から記念館の意義や展示物について説明を受けながらG7首脳の等身大パネル、実際に使用された円卓や椅子、サミットの様子を紹介する映像、各国首脳への贈呈品などを見学します。
国際会議の舞台裏に触れる貴重な体験となりました。

▲サミットで実際に使用された円卓や椅子。よく写真で見ます。
賢島を後に伊勢神宮「内宮(ないくう):正式には皇大神宮(こうたいじんぐう)」へ向かいます。
伊勢神宮は日本神道の聖地として、天照大御神を祀る「内宮」と豊受大御神(とようけのおおかみ)を祀る「外宮(げくう):正式には豊受大神宮(とようけだいじんぐう)」から成り、2000年もの歴史を持つと言われ、昔から人々の信仰を集めてきました。豊受大御神は天照大御神に食事を供える役割を担い、農業や食の神としても信仰されているそうです。
また、伊勢神宮と言えば、20年ごとの「式年遷宮(しきねんせんぐう)」が執り行われることでも知られています。前回は2013年に行われたため、次回は8年後の2033年に予定されているということです。
また、江戸時代には「おかげ参り」と呼ばれる伊勢神宮への参拝が庶民の間で大流行しました。一生に一度は訪れたい聖地として、「東海道」や「熊野古道」から続く「伊勢路」を多くの人々が行き交ったということです。
伊勢神宮「内宮」に到着後は、「宇治橋」近くの「おはらい町」で昼食をとり、案内役の方と合流し、伊勢神宮に関する説明を受けながら境内を巡ります。

▲「宇治橋」を渡って「内宮」へ入ります。鳥居の柱は、「式年遷宮」で撤去された旧「正殿(しょうでん)」の柱をリサイクルして造られているそうです。

▲長さ101.8mの「宇治橋」も「式年遷宮」に合わせて20年毎に一度、架け替えが行われるそうです。

▲昔は手水舎は無く、「五十鈴川(みすずかわ)」で心身を清める「御手洗場(みたらいば)」が設けられていました。
歩くこと30分、いよいよ伊勢神宮の中心で最も格式の高い「正宮(しょうぐう)」が目の前に現れます。

▲正宮の階段から先は、写真NGとなっています。
杉林に囲まれた「正宮」につづく階段を上がります。「正宮」のご神体は「三種の神器」のひとつ「八咫鏡(やたのかがみ)で天照大御神の依り代として祀られているそうです。
一般の参拝者は「正殿」の外からの参拝となります。
ここでは、「個人の願いを伝えることは控えるよう」聞いていましたが、いざ「正殿」の前に立つと個人の願いは出てこず、おのずと「感謝」を伝えたい気持ちになります。不思議な感覚でした。
「正宮」での参拝を終え、伊勢神宮「内宮」をあとにします。
伊勢自動車道から東名阪自動車道を通り、名古屋駅まで移動し研修を終えました。
天候にも恵まれ、2日間にわたる研修を無事に終えることができました。
今回の研修テーマは「道」。
人は古来より「熊野詣」や「伊勢参り」に象徴されるように、神社仏閣を心の拠り所としてきました。それらを結ぶ「道」は、単なる移動手段ではなく、人々の祈りや文化の記憶、自然との共生など、さまざまな意味を内包していました。
社会インフラの整備に携わる私たち建設コンサルタントにとって、今回の研修は、技術と感性の接点を改めて見つめ直す貴重な機会となりました。
社員の皆さま、2日間の研修、本当にお疲れ様でした。
【総務部:室屋】